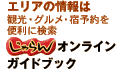|
|
|||||||||||
駅の改札前で同行者たちと落ち合い、蕎麦屋に入った。そこで、僕は母の葬儀のことを話した。 「それはおつらいでしょう……」 同行者の一人が悲痛な顔で僕に言った。そのようなことはあまりない、と正直に話した。みんなは奇異な目で僕を見た。僕が大学に入り一人暮らしをはじめるとき、すでに母は体を悪くしていた。死ぬことを医者に言われており、里帰りするたびに母を見るのはこれが最後かもしれないと考えた。何年も前に別れの心構えはできており、それが現実となっただけだった。 妙高へ向かい、様々なものを見聞きした。台風が日本に近づいており、その影響で雨が降っていた。山寺薬師の延命清水を見たのは二日目のことだった。山特有の急なカーブを幾度か車で越えた先にそれはあった。夏だというのに蝉の声はせず、車から下りた途端、水の落下する腹に響くような音が耳に入った。 五メートル程度の高さから水が勢い良く落ちていた。周囲は木々が茂っており、伸びた枝葉が落下する水に当たっていた。落ちる水はその枝で弾けるほど弱くはなく、木の枝を下へ押さえつけるようにしていた。滝のそばに岩壁から透明な水の出ている一画があった。飲めば長生きできるという延命清水だった。 写真撮影をして僕以外の者は斜面を登って行った。上へ向かったところに薬師堂という寺があった。しかし僕はその場に残り清水の出る様を眺めていた。雨がその日も降っており、他に見物客はいなかった。僕は傘を差さずに立っていた。肌に細雨が静かに当たり、それが滝からくる水煙のせいであるようにも感じられた。だれかの話していた延命清水に関する説明を思い出していた。清水は薬師堂の下を通り、こんこんとわき出て、日照りでも大雨でも水量は変わらずいつも一定だという。 僕はふと、急須を持った母の姿を思い出した。母は、僕の飲んでいる湯のみの茶が減っていると、すぐに急須から注ぎ足した。だから茶の量は減らず、常に同じ高さへと保たれていた。僕はそのことを特別に意識しなかった。それにしても、急須を持ち人の湯のみを観察して茶の量を一定に保つ母はなんと変な人だろう。その様と延命清水の逸話が心の中で重なった。 おそらくそれは母のやさしさの現われだったにちがいない。母は僕を生み、育てる間、変わらず湯のみへ茶を注ぎ続けた。僕の湯のみを見続けて、減ったと思えばまた注ぐ。僕が大学に入り、一人暮らしをするために家を出るまでそれが続いた。その母はもういない。目の前で湧き出ている清らかな水を見つめながら初めて母の死が心に迫ってきた。心臓を握り締められたような息苦しさに襲われ、僕は上を向いた。鬱蒼とした木々が灰色の雲に向かって伸びている。濡れそぼる杉の葉の先端ひとつひとつに水滴が膨らみぶら下がっている。それらが光を集めて薄暗い森の中で無数の白い星のようだった。 もっと雨が降ればいい。そして服を濡らし、顔を濡らし、山を下りてきた同行者たちに再会しても大丈夫なようにしてほしい。会社で僕は泣き顔を見せるような性格付けはなされていないのだ。弱い人間だと思われてはならない。自分は一人で生きていく。しかしもうしばらくの間、水の落ちる音に包まれてそっとさせていてほしい。なぜなら目を閉じて見える清らかな水流の向こうに母の顔があるからだ。神に祝福された清水。いつまでも透明であればいい。いつまでも変わらぬものを見せてほしい。それがきっと人々を生かすだろう。頬に霧のような雨が当たっていた。 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| いつかの新潟 TOPへ | |||||||||||||||
 おつ・いち
おつ・いち