宿番号:379260
【全16室】 秘湯と越後の味覚を味わう 国登録有形文化財の宿
越後長野温泉 嵐渓荘のお知らせ・ブログ
- 宿泊施設からのお知らせ
- お知らせ一覧をみる (118)
- 施設ブログ
-
- 2025年5月 (0)
- 2025年4月 (0)
- 2025年3月 (1)
- 2025年2月 (0)
- 2025年1月 (0)
- ブログ一覧をみる (156)
宿泊施設ブログ
-
施設のおすすめ
「嵐渓」の由来【Part.2】
更新 : 2019/6/12 11:26
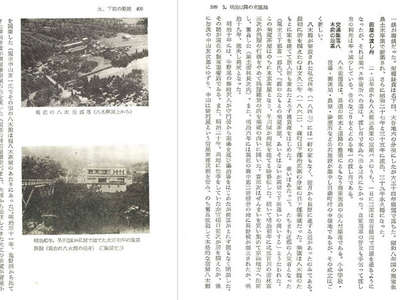
とにかく「嵐渓」は素晴らしい桃源郷のような場所だ!
そして大和朝廷時代の皇子にも、平安時代の皇子にも縁のある土地だ!
と強く訴えられています。そして、最後はこのように序文を終えます。
「我が嵐渓風光の美を世上に紹介すると共に、我が親愛なる青年諸氏が郷土の美を知り、その愛郷心を振起せられんが為なり」
著者はよっぽど「嵐渓」に思い入れのあった方なのだろうなと感じました。
現代の「嵐渓」に暮らす青年諸氏の私もグッときました。
そこで、著者の「小柳一蔵」さんについて調べたところ以下の記事を見つけました。
小柳一蔵(かずぞう)
明治元年(1868)-大正12(1923)
嵐渓史を著した他に、五十嵐神社の県社昇格に生涯を捧げた方でした。
最後は自分の命をかけて嵐渓をそして五十嵐神社を世に知らしめした。凄い方でした。
嵐渓史の巻頭に「嵐渓医院」という明治時代の病院の写真が掲載されています。
同じ写真は「下田村史」にも掲載されていたのを思いだしました。
今回のBlog記事の先頭に載せた空撮画像にある橋のたもとの建物。
これが明治時代に建てられた「嵐渓医院」です。
※実は空撮ではなく、八木ヶ鼻頂上から撮影された画像ですが。
この画像が撮影された頃には「八木館」という旅館として建物は利用されはじめていました。
その経緯も下田村史に載っています。
「嵐渓医院」のお医者さんは、この建物から別の場所に移動して医者を続けました。
その移った先というのは画像中央右にある川に出張った建物です。
さらに時代は下って第二次大戦終戦後、そちらの移転先の建物にもお医者さんはいなくなります。
その空いてしまった建物は「嵐渓荘別館」としてリノベーションされ、数年営業されました。
そしてその後は我が家の自宅となり、2019年現在はピアノ教室と嵐渓荘社宅になっています。
「嵐渓荘」という名前自体は、終戦後に観光旅館として再出発するとき、、
それまでは八木鉱泉とか妙の鉱泉とか温泉地名だけで宿に名前はなかったので、再出発するにふさわしい宿名を新聞で公募したと私は聞いています。
そして、その応募作品の中から選ばれたのが「嵐渓荘」だったとのこと。
たぶん本当の話だと思います。いい名前だなあとも思います。
今回「嵐渓史」を書いた小柳一蔵さんの熱い想いを知りまして、
あらためてこの「嵐渓」エリアを、桃源郷とまではいかなくても、
自然とともに豊かに暮らせる場所として後世に残していけるようにしたいと、強く思った次第です。
他のホテルを探す場合はこちら