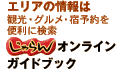|
|
|||||||||||
デスクの上には片付けても片付けても書類があり、家の中には洗っても洗っても洗濯物がある。 それらひとつひとつが細胞分裂してエンドレスに増殖を続けるているように思えて、私はついに東京駅で降りていつものとおりに会社に行くことができずに思わず上越新幹線に乗ってしまったのである。 出勤時間に出てきてしまったため、お昼前には長岡についた。 トンネルのたびに目を閉じ、トンネルを出たあたりで目を開け、またトンネルで目を閉じ、ということを繰り返しているうちに、たった一時間と少しでもう風景が別の世界になっていた。 カバンも服も出勤用で、「旅行」といういでたちではなかったが、 なぜか心の中が風通しが良くなったようにすっきりしはじめた。 それはデスクの上の書類や散らかっている洗濯物がここにはないからかもしれない。 そして私がここにいることを誰にもしられていないことがなおいっそう、私を快適にさせているのにちがいない。 長岡の駅でクロワッサンをひとつ買って、駅の電話ボックスから会社に連絡した。 「今、病院まで来たんだけど、調子が悪くて…」 電話口に出た後輩はたいして疑う様子もなく、 「そうですか。お大事にしてください」 と言った。 きっと後輩のデスクの上にも今頃、うずたかく書類が積まれているのだろう、と思うと、私の胸は少し痛んだ。 電話ボックスを出たとたん、 「そう。すごく夕日がきれいでね」 という声が私の耳に飛び込んできた。 「じゃ、そこ行く?」 見れば、まだ初々しい新入社員という感じのショートカットの女の子とその先輩の初デートという様子のカップルがいた。 彼女の生まれたところには夕日がものすごく美しく沈む公園があるという。 聞くとはなしに聞いているうちに私も興味をそそられた。 彼女の言っていた地名は「出雲崎」である。 「だってその名前が『良寛と夕日の丘公園』っていうんだよ」 彼女が見上げて言うと、青年は笑って、 「それじゃあ、夕日はきれいなはずだよね」 と言った。 青年は先輩ではなくて東京から来た人かもしれないな、と私はいろいろ想像した。 「信越線で柏崎まで行って、そこから越後線で出雲崎です」 と若い駅員さんに丁寧に教えてもらって、私は列車に乗った。 恋人同士になりそうなふたりはきっと車で行くのだろうが、私は気楽な一人旅だ。 日の入りが何時かはわからないが、きっとまだ充分に時間はあるだろう。 階段を上り、その公園に着いた私はクロワッサンをかじりながら沈む夕日を待った。 例のカップルはもう先についていたので、邪魔しないように私は少しはなれたベンチに座った。 彼方に見える島影は佐渡だろう。 大きな「太陽」はある角度まで落ちると、それは「夕日」というものに変化する。 赤からオレンジに、やがてピンクにと海を染めていく。 はしゃいでいたカップルももう夕日の美しさに言葉を発さなくなっていた。 私はもう半分、海に沈んだ夕日を見ながら、今夜のうちに東京に戻ろう、何もかもいやになったらまたここへくればいいのだから、と考えていた。 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| いつかの新潟 TOPへ | |||||||||||||||
 しまむら・ようこ
しまむら・ようこ