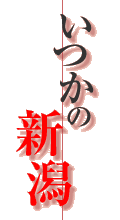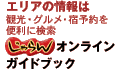|
|
|||||||||||
「野沢菜が雪の下になった」と、お婆ちゃんの眉がハの字を描く。けれども、行きずりの旅人に、この風景はご馳走だ。 旅行者という存在は一種、身勝手なものである。生活の苦労がないからか、その地方の出来事すべてを「つまらなかった」「面白かった」と得手勝手に分類し、思い出袋に詰めてしまう。自戒し、反省すべきだが、その勝手が許されるのが旅人という存在でもある。 雪は山を白く装い、私の心を歓喜に導く。眼前に並ぶ料理の品も、紛れもないご馳走だ。 ふっくらと艶やかな炊きたてご飯に、秋ならではの茸の数々。生でも甘い大根の鮮烈な歯触りもさりながら、山の幸には心が躍る。 鍋に入った赤肉は、近くの畑にいた熊だ。鹿と山菜は裏の山から。水も山からもたらされ、宿も山の中にあり、温泉、空気、すべてがすべて、この土地なくては得られない。 終日、山に包まれて甘やかされているような、優しい幸福感がある。それを何の屈託もなく甘受できるのはやはり、旅だからに違いない。黄金の雫を集めたような美酒に陶然としていると、「ほら。お神楽が始まる」と誰かが私を急き立てた。 「お神楽?」 「獅子舞と手踊りと」 連れ出された夜の中、川沿いをずっと歩いていくと笛や太鼓の音が聞こえた。明々と点いた電灯の下、村人達が艶やかな衣装を着けて笑っている。 「どうぞ、上座に」「遠くから来て、疲れたろ」 促されるまま席に座ると、私以外にも数人の旅人が畏まっていた。中のひとりが、恐縮しきった顔で囁きかけてきた。 「僕達は今、神様の席に座っているんです……」 神楽は、神のためのもの。それを見せて頂ける、私達の立場は神に等しい。上座は神座、と彼は語った。驚いて神楽の舞台を見やると、獅子頭を被った青年が真っ赤な口を開けながら、こちらに迫ってくるようだった。笛と太鼓が鳴り響く。 酒に酔って、舞いにも酔ったか。畏れ多いを通り過ぎると、眼前はただ、神秘に染まる。 とりどりの衣装の錦が、山の紅葉に変化した。囃子は谷を渡る風。一座をまとめる男衆が凛々しい山神に姿を変えて、それに従う若い衆は獣や木々の精霊となる。 清流の化身のような女性が、穏やかな声で語ってくれた。 「ここの鎮守は奴奈川姫という女神様。女神は村の脇にある川をここまで上って、戻っていったの。鎮守の社は姫神のそんな魂を愛おしみ、村人達が祀ったのです」 どうして、この山に来て、女神は帰っていったのか。ぼんやり考えている隙に、通る声が辺りに響いた。 獅子が私達の影を祓った。同時に、私は姫神の気持ちがわかったような気がした。 気分転換でも遊山でも、旅に出掛ける人は皆、充ちたらぬ思いがあるゆえに、あちこち彷徨い歩くのだ。私自身、気づくところはないが、顧みるなら確かに何か、辛いものがあった気がする。悪魔として祓うべき、陰気が日常の澱として心に溜まっていたと感じる。 女神もきっと、断ち切りたい何かを持っていたのだろう。そして旅人となり、ここに至って、優しい神々にもてなされ、心に潜む魔を断った。今の私と同様に。 「存分に甘えていいんだよ」 どこかで声が聞こえた気がした……。 翌日、私は神楽を見た旅人達と、女神を祀った神社に詣でた。思ったとおり、女神の社は山に抱かれ、まどろむようだ。 奴奈川姫は翡翠の女神。春が来れば、この山は瑞々しい翡翠の葉で充ちる。 旅人達も山神に甘えきったそののちに、踵を返して、それぞれの土地で小さな春を育む。 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| いつかの新潟 TOPへ | |||||||||||||||
 かもん・ななみ
かもん・ななみ