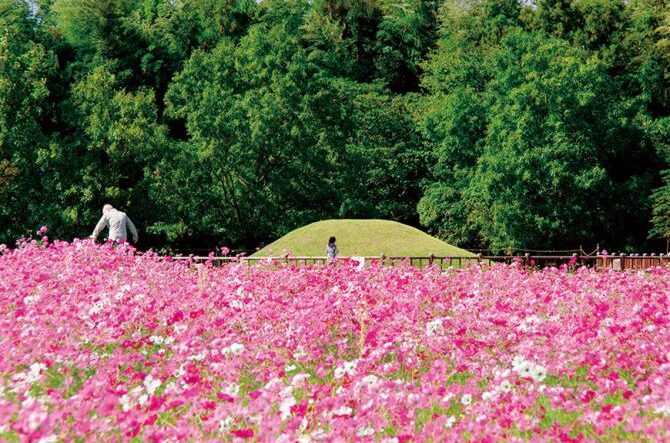新しい年の始まりに、厄払いや厄除けに行く人も多いのではないでしょうか?そこで今回は、厄除けや厄払いにご利益があると言われている神社やお寺を全国から厳選!
遠方からも参拝客が訪れるパワースポットや、心が洗われる絶景、ちょっと変わったスポットなど、バリエーション豊富にご紹介します。ぜひチェックして参拝の計画を立ててみてくださいね。
※口コミはじゃらんnet観光ガイドから抜粋しました。
【青森県】病厄除守護神 廣田神社
天明の大飢饉以来、病厄除の守護神として歴史を受け継ぐ古社

天明の大飢饉の際、徳川将軍の命によって疫病を落ち着かせるよう廣田神社に祈願したところ、災いであった疫病を祓うことができたため、あらゆる災難・厄・病を祓い除く“病厄除”の守護神として、全国より崇敬を集めるようになったそう。
内外から起こるあらゆる厄災を祓う「病厄除」の御神徳をいただくことができ、祈祷をした人には、江戸幕府から授けられた箱入りのご神札を模した白木造箱入りの特別病厄除神札が授与されます。
青森県青森市長島2-13-5
自由【社務所・授与所】8時30分~16時30分
なし【社務所・授与所】水
【電車】JR青森駅より徒歩15分【車】東北自動車道青森ICより20分
あり(無料)
「病厄除守護神 廣田神社」の詳細はこちら
「病厄除守護神 廣田神社」の口コミ・周辺情報はこちら
【福島県】伊佐須美神社
およそ2100年の歴史を有し、鎮護国家の役割を担ったとされる総鎮守

国家鎮護の神として広く人々を幸福に導く神様。特に運や縁結び、事業育成などにご利益があると知られており、八方除東北総鎮護とも称えられ信仰されています。
こちらで授与してもらえる「強運御守」は、方位をはじめ家相や日柄、厄年、星の巡りに至るまで、日々営む生活のなかで受けると言われている災難凶事を除いて福徳吉祥を招き、大難を小難に小難を無難にするものです。
授与の際に中指に下げて神域を散策し、自身の手でご神気をお守りに込めることで、更なる強運を添えられると言われています。
また「厄割玉」という縁起物は、素焼きの玉に自分の名前を書き、身体の不調な部分を撫でて厄割石に投げ割ると厄が祓われるとされています。
会津には、何度も行っているのに、初めて行きました。こんな、素敵な所が、あったのですね。池には、鯉が、沢山泳いでいて、餌も、あげることもできて、楽しかったです。
(行った時期:2024年10月)
以前に御朱印をお願いしたものの待ち時間に間に合わず未完成でしたのでお願いしました。参道には風鈴の小道ができていて心が休まりました。
(行った時期:2024年8月)
福島県大沼郡会津美里町字宮林甲4377
参拝自由【御祈祷受付】9時~15時【御朱印・授与所・宝物殿】9時~16時
なし
【宝物殿拝観料】大人300円、18歳以下150円
【電車】JR会津若松駅より会津バスで40分※横町下車徒歩3分【車】磐越自動車道新鶴スマートICより15分・会津若松ICより30分
あり(無料)
「伊佐須美神社」の詳細はこちら
「伊佐須美神社」の口コミ・周辺情報はこちら
【栃木県】佐野厄よけ大師
関東三大師として知られる、長く続く祈願寺で幸福を願う

944年、藤原秀郷が現在の佐野城跡である春日岡に創建したのが起源とされています。1600年の佐野城の築城に際し、今の場所に移転されたと伝えられています。
正式名称は「春日岡山 転法輪院 惣宗官寺」。正月に行われる厄払いに加え、厄除け・方位除けなどの祈願や水子供養は毎日行われているそうです。
境内にはふくよかで可愛らしい「お掃除小僧(子育地蔵尊)さん」という笑顔の地蔵も。参拝する親子連れがタワシで体を洗うことで、丈夫な子、まめな子、よく働く人間に育つとの言い伝えがあります。親子で参拝した際にはぜひ立ち寄ってみてください。
10時到着でした。9日晴れていましたがとても寒い日だったんだけど人出は全く関係のない模様でした。お店などだいたいはすでに販売されていましたよ。今年も行けて良かったです。
(行った時期:2024年1月)
栃木県佐野市金井上町2233
参拝自由【祈願受付】8時20分~16時40分※年末・1月中は変更あり
なし
【電車】東武鉄道佐野市駅より徒歩10分【車】東北自動車道佐野藤岡ICより10分
あり(無料)
「佐野厄よけ大師」の詳細はこちら
「佐野厄よけ大師」の口コミ・周辺情報はこちら
【埼玉県】妻沼聖天山
精巧につくられた本殿が魅力な寺院で、良い縁を結ばれに

1760年に再建された妻沼聖天山歓喜院の本殿「聖天堂」は、日光東照宮の流れをくんだ、日光を彷彿とさせる絢爛豪華な装飾建築です。その精巧さゆえに“埼玉日光”と言われ、国宝に指定されています。
2003年10月から約7年間の歳月をかけ、250年の時の流れとともに生じた傷みや、剥落した彩色を建立当時のように美しく蘇らせる「平成の大修理」が行われました。現在は一般公開中です。
厄除けでは悪縁や悪疫を除き、厄年・方位除けのご利益があります。また、妻沼聖天山は縁結びのパワースポットとしても知られ、恋愛の縁をはじめ、家内安全・商売繁盛・厄除け開運・交通安全・合格祈願など、あらゆる願いに良いご縁のご利益をいただけるのだそうです。
埼玉県熊谷市妻沼1511
【平日】10時~15時30分【土・日・祝】9時30分~16時30分
なし
【拝観料】大人700円、中学生以下無料
【電車】JR熊谷駅より朝日バスで30分※妻沼聖天前下車徒歩すぐ【車】北関東自動車道太田桐生ICより40分、関越自動車道東松山ICより40分
300台(無料)
「妻沼聖天山」の詳細はこちら
「妻沼聖天山」の口コミ・周辺情報はこちら
【千葉県】千葉神社
厄除開運・八方除の“妙見さま”の総本宮。朱塗りの社・神橋は必見

御祭神は北極星・北斗七星の御神霊「北辰妙見尊星王」で、人間の運命・方位を司る神様として、厄除開運・八方除の御神徳がいただけるとされています。
千葉神社は、上下に2つの拝殿を有する2階建ての社。すぐ横の摂社「千葉天神」は、学問の神様・菅原道真公を御祭神としており、受験合格や職務上の安全祈願におすすめです。
また、境内の妙見池には朱塗りの2つの神橋「ねがい橋・かない橋」がかかっています。写真映えするスポットなので、願い事を思い浮かべながら散策した後は記念撮影も忘れずに。
娘の3歳時の七五三参りから10年が経ち、思い出確認と娘にルーツを教えてあげる為に10年ぶりに新潟からお参りに来ました。10年前と変わらず素敵な神社でした。
(行った時期:2024年8月)
千葉駅から歩くこと15分弱といったところでしょうか。公園のようなところの中にありました。千葉神社と千葉天神がならんでいます。何か他とはちょっと違う感じがしました。
(行った時期:2024年8月)
千葉県千葉市中央区院内1-16-1
6時~18時
なし
【電車】JR千葉駅より徒歩10分【車】京葉道路穴川ICより10分
なし※近隣に有料駐車場あり
「千葉神社」の詳細はこちら
「千葉神社」の口コミ・周辺情報はこちら
【東京都】西新井大師
空海が創建した悪疫退散・厄除けにご利益があるとされるお寺

826年、弘法大師が創建したと伝わる「五智山遍照院総持寺」。真言宗豊山派の寺院です。
800年代、悪疫流行に悩む村人を救おうと祈祷を行ったところ、枯れ井戸から清らかな水が湧き、病がたちどころに平癒したとされる伝説から「厄除開運」の霊場として知られています。その井戸がお堂の西側にあったことから、地名が「西新井」になったのだとか。
境内の3カ所には約100品種、2500株のぼたんが植えられ、“ぼたん大師”とも称されています。
東京都足立区西新井1-15-1
【境内】6時~20時【本堂】8時~18時※12月30日~1月は変更あり
なし
【電車】東武鉄道大師前駅より徒歩5分【車】首都高速道路加平出口・扇大橋出口より15分
なし
「西新井大師」の詳細はこちら
「西新井大師」の口コミ・周辺情報はこちら
【神奈川県】川崎大師
平間兼乗が創建。厄除けの護摩祈祷を修行しているお寺

「成田山新勝寺」、「高尾山薬王院」とともに数えられる、真言宗智山派三大本山の一つ。全国から大勢の参詣者が訪れます。
さまざまな災厄を消除する“厄除けのお大師さま”として古くから親しまれており、本尊厄除弘法大師像は、平安時代に夢のお告げを受けた武士の平間兼乗によって海中から引き揚げられたという逸話もあります。
広々とした境内には八角五重塔や不動堂、薬師殿など多くのお堂が並んでいるので、散策しながら見て回るのもおすすめです。
表参道、参道前の商店街から、久寿餅やだるま、痰きり飴などの古風なお店が並んでいて、雰囲気いいですね。京急の駅からやや歩きますが、楽しみながら、お店を覗いているうちに着いちゃいました。
境内も立派な大本堂、不動堂や五重塔など、見所が多々あって、良い時を過ごせました。驚いたのは、相撲取りの北の海関の銅像があったこと。相撲に関連があるのかと思いましたが、違う謂れでした。
(行った時期:2024年3月)
昨年の達磨を奉納するために1月の半ばに参拝しました。多くの参拝者で賑わっていました。門前の商店街で名物の飴を買い求め、家族への土産にしました。
(行った時期:2024年1月)
神奈川県川崎市川崎区大師町4-48
大本堂開扉時間【10月~3月】6時~17時30分(毎月21日は5時30分~)【4月~9月】5時30分~18時(毎月20日は~21時。1月は変動あり)
なし
【電車】京急電鉄川崎大師駅より徒歩8分【車】首都高速道路大師出口より5分
あり(無料)
「川崎大師」の詳細はこちら
「川崎大師」の口コミ・周辺情報はこちら
【神奈川県】寒川神社
全国唯一の八方除の神社。福徳開運をもたらす御霊験あらたかな神社

「寒川神社」は、相模國一之宮と称され、八方除の守護神として約1600年の歴史を持つ神社です。御祭神は、寒川比古命と寒川比女命。二柱の神様は関東地方を開拓し、衣食住など人間生活の根源を開発指導した、関東地方の親神様として崇敬されています。
八方除とは、地相・家相・方位・日柄などに起因するすべての災難をとり除き、家業繁栄・福徳円満をもたらす御神徳で、生活に限りない恩恵をもたらすと言われています。寒川神社の御祈祷は、神職と直接お話をすることが特徴。
「寒川神社」は相模川がおりなす豊かな自然が残る杜の中に鎮座しています。清らかな空気が流れる境内で、身も心もリフレッシュできますよ。
参道は木々も多く空気も違う感じがしました 手水場を済ませて本殿へ・1年遅れと成ってしまいましたが、念願の参拝お礼と感謝の気持ちでお参りさせていただきました。帰りにお守りと御朱印を頂いて帰ってきました! 素晴らしい神社なので又お参りに伺いたいと思います!!。*駐車場も無料で広々なので、駐車もしやすく安心です。(一部抜粋)
(行った時期:2024年11月)
仕事関係で近くまで行くことがあり有名な神社だとは知っていたのでぜひ行ってみたいと思っていました。静かな木々を取って本殿まで行き参拝、御朱印を頂き、横の御土産屋さんで有名な団子等を買って帰りました。高速のICも近くにあり便利でした。
(行った時期:2024年11月)
神奈川県高座郡寒川町宮山3916
参拝自由【御祈祷】8時~17時
なし
【電車】JR宮山駅より徒歩5分【車】圏央道寒川北ICより3分
あり(無料)
「寒川神社」の詳細はこちら
「寒川神社」の口コミ・周辺情報はこちら
【静岡県】法多山 尊永寺
厄除観音で知られる古刹。季節ごとのイベントやカラフルな守り袋にも注目

約1300年続く「法多山 尊永寺」。厄除観音として知られ、地元の人はもちろん、県外からも多くの参拝客が訪れます。
また、厄除け祈願と合わせておすすめなのが、江戸時代から変わらない形と味で長年愛されてきた串だんご「厄除だんご」。体を表現した5本の串にささった団子に、厄除けの意味が込められています。
春は桜、梅雨頃にはあじさいや青々としたモミジ、秋には紅葉やイチョウが彩る境内では、四季の移ろいを感じることができます。
尊永寺では年間を通してさまざまなイベントが行われており、春のさくらまつり、5月下旬のホタル祭りのほか、7月の万灯祭では4000基の灯籠が灯ります。夏に行われる風鈴まつりは、約1500個の風鈴が奏でる爽やかな音色が境内に響くなんとも風流なイベントです。
また、約30種類の柄から選べるお守り「古代裂守袋(こだいぎれまもりぶくろ)」(300円)にも注目!年初めに新柄の販売があり、柄によってご利益が異なる想いの趣向を凝らしたお守り袋です。
静岡県袋井市豊沢2777
参拝自由【授与所】8時30分~16時30分
なし
【車】東名自動車道袋井ICより25分
2000台(民間駐車場)
「法多山 尊永寺」の詳細はこちら
「法多山 尊永寺」の口コミ・周辺情報はこちら
【岐阜県】洲原神社
長良川の清流に災厄を流して厄払い。縁結びや子授け祈願でも知られる神社

神社門前に清流長良川が流れる風光明媚なロケーションにある「洲原神社」。みそぎをして神々を生んだ伊邪那岐命(いざなぎのみこと)を御祭神として祀り、古くから霊峰白山への登拝の清めの場として、みそぎ祓いの神社と位置づけられています。
厄払いの御祈祷では、紙の人形(ひとがた)にけがれを移して長良川に流します。清らかな川の流れと共に厄もキレイに落とすことができるのだとか。江戸初期から中期にかけて建造された社殿群が今もそのままの形で残る、貴重な文化遺産で御祈祷を受けることができます。
また、縁結びなら境内の夫婦桧に願い事をするのがおすすめです。男性は女桧、女性は男桧を抱きかかえると良縁に恵まれると言われています。境内東端には子授け安産の霊石もあります。
岐阜県美濃市須原468-1-1
参拝自由【社務所】9時~16時
なし
【電車】長良川鉄道洲原駅より徒歩10分【車】東海北陸自動車道美濃ICより15分
あり(無料)
「洲原神社」の詳細はこちら
「洲原神社」の口コミ・周辺情報はこちら
【岐阜県】三輪神社
厄除け、良縁結び、交通安全などご利益があるとされるダイコクさま

「三輪神社(みわじんじゃ)」は岐阜県揖斐郡(いびぐん)の総鎮守として古来より崇められてきました。御祭神は大物主大神(おおものぬしのおおかみ)で、万の縁を結ぶ神様です。
境内の「さわりダイコク」や「なでうさぎ」など、よく触ることで大神様の良縁結び、厄除け、交通安全など多くのご利益を受けられると言われています。
約4000坪の敷地には大樹が繁茂しており、自然豊かで厳かな雰囲気が漂っています。銭洗い弁財天も鎮座しているので、金運のご利益をいただくのもおすすめです。
岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪1322
参拝自由【社務所】9時~16時30分
水
【電車】養老鉄道揖斐駅よりはなももバス(要予約)で10分※高砂広場下車徒歩1分【車】東海環状道大野神戸ICより15分
あり(無料)
「三輪神社」の詳細はこちら
「三輪神社」の口コミ・周辺情報はこちら
【愛知県】尾張大國霊神社(国府宮)
厄除けの「はだか祭」で知られる、尾張に古くから鎮座する神社

毎年旧暦の1月13日に行われる厄払いの「はだか祭」で知られる神社。尾張大國霊神(おわりおおくにたまのかみ)を御祭神とし、尾張の総鎮守神、農商業守護神、厄除神として地元で厚く信仰されています。奈良時代、国衛(こくが)に隣接して鎮座していたことから尾張国の総社と定められ、国司自らが祭祀を執り行う神社だったことから、通称“国府宮”として広く知られています。
境内には5つの大きな自然石を円形に配した磐境(いわくら)と呼ばれる原始的で古い斎場もあり、この地で社殿が建てられる以前から信仰を集めていたことがうかがえます。約550年前に建立された楼門、約350年前に建立された拝殿は、共に国の重要文化財に指定されています。
「はだか祭」の神事では“神男に触れれば厄落としができる”との言い伝えがあります。4日間にわたって機会が設けられているので、タイミングを合わせて参拝するのもおすすめです。
愛知県稲沢市国府宮1-1-1
9時~16時
なし
【電車】名古屋鉄道国府宮駅より徒歩5分【車】名神高速道路一宮ICより15分
あり(無料)
「尾張大國霊神社(国府宮)」の詳細はこちら
「尾張大國霊神社(国府宮)」の口コミ・周辺情報はこちら
【滋賀県】神田神社
厄除けの名社。七福神社や手が届く鳥居、昔ながらのおみくじにも注目

神社でありながら不動明王(仏像)を祀る神社です。創建は約1200年前の平安時代初期に遡り、神社が位置する真野(滋賀県大津市)は、琵琶湖のほとりに位置する風光明媚な土地として和歌にしばしば詠まれました。
主神は地域の守り神・氏神で、厄除けの御神徳があると言われています。末社の七福神社は七つの社が合わさったような神社です。それぞれ異なる御神徳が得られる七柱(七神)が祀られているため、訪れる人に合った神様が見つかるはず。鳥居の上部(笠木)に触れることができる「手が届く鳥居」や昔ながらのおみくじにも注目してみてください。
滋賀県大津市真野4-7-2
8時~17時
なし
【電車】JR堅田駅より徒歩20分【車】湖西道路真野ICより5分
あり(無料)
「神田神社」の詳細はこちら
「神田神社」の口コミ・周辺情報はこちら
【京都府】八坂神社
厄除け・縁結びの神“祇園さん”。「祇園祭」や「をけら詣り」も必見!

「八坂神社」は、全国の祇園社の総本社です。厄除け・縁結び・商売繁盛などさまざまなご利益をいただける神で、“祇園さん”の呼び名で親しまれています。創祀は656年で、京の都に大流行した疫病を鎮めたと伝わり、以来、厄除けの社として信仰を集めています。
現在でもこの社で執り行われている日本三大祭の一つ「祇園祭」は京都の代表的祭事です。毎年7月1日の「吉符入」に始まり31日の「疫神社夏越祭」で幕を閉じるまで、1カ月にわたって各種の神事・行事がくり広げられます。
また、師走の風物詩である「をけら詣り」は厄除におすすめ。“をけら火”を吉兆縄に移してくるくる回しながら家に持ち帰り、その浄火を火種にしてお雑煮を食べると無病息災が叶うと言われています。
2020年12月に八坂神社本殿は国宝に指定され,他26棟の重要文化財追加で,国宝1棟と29棟の重要文化財の建造物が境内に建ち並んでいます。
(行った時期:2024年10月)
祇園祭りが八坂さんの1か月かけてんおお祭りと知って、祇園祭りの時期に行き、京都の夏を感じています。河原町から散歩しながら行けます。
(行った時期:2024年8月)
京都府京都市東山区祇園町北側625
参拝自由【社務所受付】9時~17時
なし
【電車】京阪電気鉄道祇園四条駅より徒歩5分、阪急電鉄京都河原町駅より徒歩8分【車】名神高速道路京都東ICより20分
なし
「八坂神社」の詳細はこちら
「八坂神社」の口コミ・周辺情報はこちら
【大阪府】難波八阪神社
勝運(商運)を招く、巨大な獅子の絵馬殿が大迫力!

「難波八阪神社」は、後三条天皇の1069年~1073年頃から祇園牛頭天王(ごずてんのう)をお祀りする古社として世間に知られてきました。
境内にある、巨大な獅子頭をかたどった、高さ12m、幅11m、奥行10mの大きな舞台・獅子殿は必見!大きな口で勝利を呼び邪気を飲み込み、勝運(商運)を招くと言われ、受験生・スポーツ選手・企業などの参拝者が多く訪れます。この獅子殿に祀られている素盞嗚尊(すさのおのみこと)は、八岐大蛇(やまたのおろち)を退治した神様として知られ、厄除けや病気退散のご利益があると言われています。
毎年1月第3日曜日に行なわれる綱引神事は、八岐大蛇(やまたのおろち)を退治した際に、民の困苦を除いたという故事に基づいて始められたもの。2001年には、大阪市で初めての無形民俗文化財に指定されました。
大阪府大阪市浪速区元町2-9-19
9時~17時
なし
【電車】Osaka Metro・南海電鉄なんば駅より徒歩8分【車】阪神高速道路1号環状線湊町ICより5分
なし
「難波八阪神社」の詳細はこちら
「難波八阪神社」の口コミ・周辺情報はこちら
【兵庫県】門戸厄神東光寺
御宝前で厄除開運祈願。大阪まで一望の景色も満喫できる

兵庫県西宮市にある厄除け・厄払いで知られるお寺。全国から訪れる参詣者が後を絶たず、毎年1月18日・19日の厄除け大祭は多くの人々で賑わいます。
境内の中楼門の下には33段の「女厄坂」と呼ばれる厄年にちなんだ階段があり、一段一段登ることで厄を落とすことができるとされています。階段を登りきると高台から大阪まで見渡せるロケーションが素晴らしいと評判です。
高野山真言宗の別格本山であり、現存する厄神明王様の御宝前で厄払いができます。身代わりお守りなど厄除開運のお守りも充実しているので、ぜひ厄除開運祈願をした後に注目してみてください。
兵庫県西宮市門戸西町2-26
9時~17時
なし
【電車】阪急電鉄門戸厄神駅より徒歩10分【車】名神高速道路西宮ICより20分
あり(無料)※1月、2月は車での参拝をご遠慮ください
「門戸厄神東光寺」の詳細はこちら
「門戸厄神東光寺」の口コミ・周辺情報はこちら
【奈良県】岡寺
西国三十三所の巡礼者が参拝する、厄除け祈願と巡礼の寺院

「岡寺」は、西国三十三所観音霊場の第七番札所です。また“日本で最初の厄除け霊場”としても信仰を集めています。ご本尊は「塑造 如意輪観音坐像」。塑像(土で作られた仏像)としては日本最大の大きさを誇り、岡寺大仏とも言われています。
1年を通し西国三十三所の巡礼者が参拝に訪れており、年間を通してさまざまな行事が実施されています。毎年2月初午の日と3月初午の日に行われる「厄除開運護摩供大般若法要」では、初午の日に岡寺で厄除参りをすると一年無事に過ごすことができるのだとか。
春には境内に植えられている約3000株の石楠花(シャクナゲ)が見頃を迎えます。秋には境内を囲むように紅葉が色づき、まるで紅葉のトンネルのよう。移ろいゆく季節を感じながらのお参りができます。
西国三十三ヶ所第七番札所で、明日香村の少し東外れにあります。平日の昼前に伺ったので、あまり人も居なくてゆっくり礼拝できました。紫陽花の季節になってきていて、花が綺麗になってきていて咲いていました。やはり落ち着きますね。
(行った時期:2024年5月)
飛鳥村ハーフマラソン大会参加しました。宿が若葉宿で岡寺に近いところです。最高でした。岡寺の3重の塔が凄い感動を受けました。
(行った時期:2024年3月)
奈良県高市郡明日香村岡806
【3月~11月】8時30分~17時【12月~2月】8時30分~16時30分
なし
【入山料】大人400円、高校生300円、中学生200円、小学生以下無料
【電車】近畿日本鉄道橿原神宮前駅より奈良交通バスで30分※岡寺前下車徒歩約10分【車】西名阪自動車道 郡山IC・天理ICより約40分
なし
「岡寺」の詳細はこちら
「岡寺」の口コミ・周辺情報はこちら
【和歌山県】伊太祁曽神社
神話にちなんだ木の俣くぐりで厄難除け。厄祓いの絵馬も奉納

『日本書紀』によると“日本に樹木を植えて回った神”とされる五十猛命(いたけるのみこと)を祀る「伊太祁曽神社」。古くから木の神様として信仰を集めています。
五十猛命は別名・大屋毘古神(おおやびこのかみ)として『古事記』にも登場します。木の俣をくぐらせて大国主神を厄難から救ったという神話にちなみ、この神社では実際に木の俣くぐりによる厄難除けが行なえます。
また、厄難除けの鏡文字絵馬にも注目。厄年の“負”の力を裏返して“正”に変えるという意味で、「厄」の文字を鏡文字で裏返しにしています。厄年の人は絵馬掛けに奉納するのもおすすめです。
※厄除け祈願・祈祷は原則事前予約制で1組ずつ行われる。ただし1月の繁忙期には数件一緒に案内されることもあり。
和歌山県和歌山市伊太祈曽558
【参拝・木の俣くぐり】参拝自由【社務所・授与所】9時~17時
なし
【電車】和歌山電鐵伊太祈曽駅より徒歩5分【車】阪和自動車道和歌山南ICより5分(ETC専用)
あり(無料)
「伊太祁曽神社」の詳細はこちら
「伊太祁曽神社」の口コミ・周辺情報はこちら
【島根県】安来 清水寺
木々に囲まれた石畳の先にある“厄よけの観音様”

587年に開かれた天台宗の古刹。十一面観世音菩薩をご本尊に、古くから“厄よけの観音様”として信仰されています。
千年杉も茂る境内は5万坪以上と広大で、根本堂など重要文化財が数多くあります。三重塔は実際に登ることができ、第3層からは市街地を見渡せます。
「安来 清水寺」を中心とした一帯は県立自然公園となっており、春は三重塔の周囲にソメイヨシノが咲き誇り、秋は鮮やかな紅葉の風景を楽しめます。お寺では写経や座禅体験も可能なので、参拝後に挑戦してみるのもいいですね。
※2024年12月~2025年3月の期間中は、宝物館拝観・三重塔登閣を休止
島根県安来市清水町528
9時~16時30分【祈祷受付時間】9時~16時
臨時の休業あり。公式ホームページで要確認
【三重塔・宝物館】大人500円、中高生300円、小学生100円※1週間前までに要予約
【電車】JR安来駅よりタクシーで15分【車】山陰自動車道安来ICより10分
あり(無料)
「安来 清水寺」の詳細はこちら
「安来 清水寺」の口コミ・周辺情報はこちら
【岡山県】由加神社本宮
「求めれば必ず応じてくださる」と伝わる神社。境内の備前焼大鳥居にも注目

厄除けの総本山として信仰を集める「由加神社本宮」。巨岩を御神体とする磐座信仰からはじまり、江戸時代より“こんぴらさん“として親しまれる香川県の「金刀比羅宮」との“両参り“が盛んに行われるなど、2000年以上の長い歴史を受け継いでいます。
由加の権現は、「求めれば必ず応じてくださる」という意味である有求必應(ゆうきゅうひつおう)として知られています。三が日には約35万人が参拝に訪れるほか、年間を通しても多くの参拝者が訪れています。
境内には本殿のほか、備前焼大鳥居など多くの文化財も点在しています。実際に足を運んで見てみてくださいね。
隣接する蓮台寺と併せて厄払いのお詣りに来ました。児島駅からのアクセスが悪く、タクシーでわざわざ来る人は少ないと思いますが、静かな落ち着く場所です。
(行った時期:2024年10月)
今回は倉敷の由加神社本宮に参拝しました。2月の終わりだったので好いていました。ここは2社参りとして金毘羅さんと由加神社をお参りすると縁起がいいと書いてあったのでお参りしました。駐車場から歩いて10分くらい登ったところに本宮がありました。とても神聖なかんじがしとてもよかったです。このひはとても天気が良くてよかったです。
(行った時期:2024年2月)
岡山県倉敷市児島由加2852
8時~17時
なし
【電車】JR児島駅よりタクシーで15分※由加山表参道入口より徒歩7分【車】瀬戸中央自動車道水島IC・児島ICより20分
あり(無料)
「倉敷 由加神社本宮」の詳細はこちら
「倉敷 由加神社本宮」の口コミ・周辺情報はこちら
【香川県】郷照寺
境内から臨海の宇多津の町と瀬戸大橋を望める厄除けのお寺

香川県綾歌郡の宇多津町の南、青ノ山のふもとの高台に建つ、厄除けにご利益があると言われている「郷照寺」。臨海の宇多津の町と瀬戸大橋を見晴らせる絶景スポットとしても知られています。
815年、弘法大使がこの地を訪れ、自作の尊像を刻み厄除の誓願をしたことから、“厄除うたづ大師”として信仰を集めています。
1288年、時宗の開祖・一遍上人によって浄土易行の法門の伝統が加わり、真言・念仏の2教の法門が伝わりました。真言宗と時宗の両宗にわたるお寺です。
香川県綾歌郡宇多津町1435
8時~17時
なし
【電車】JR宇多津駅より徒歩20分【車】瀬戸中央自動車道坂出北ICより9分
あり(無料)
「郷照寺」の詳細はこちら
「郷照寺」の口コミ・周辺情報はこちら
【徳島県】薬王寺
厄除薬師如来がご本尊。厄坂を登って厄払い

「四国八十八ヶ所霊場二十三番札所」の「薬王寺」。地元の人からは“おやくっさん”と親しまれ、年間約80万人が参拝に訪れます。
厄除を誓願して刻まれた厄除薬師如来をご本尊とし、毎朝、護摩祈祷を行っているほか、参拝者の申し込みによる厄除や祈願成就を受け付けています。
境内には33段女厄坂、42段の男厄坂、61段の男女還暦厄坂と、3つの厄坂があります。厄坂の石段の一段ずつにお賽銭を置いて登ると厄が落ちると言われています。
お遍路で行きました~山の寺で景色も良く、良い感じです。車で行くのもそれほど困難では無かったので、行きやすかったです。
(行った時期:2024年11月)
徳島県海部郡美波町奥河内字寺前285-1
参拝自由【納経所】8時~17時
なし
【電車】JR日和佐駅より徒歩5分【車】徳島自動車道徳島ICより70分
あり(無料)
「薬王寺」の詳細はこちら
「薬王寺」の口コミ・周辺情報はこちら
【鹿児島県】釜蓋神社(射楯兵主神社)
勝負事や開運・開拓・厄除け・武運長久のご利益で知られるパワースポット

「釜蓋神社(射楯兵主神社)」は、古くから武士道や勝負の神様として畏敬されていました。戦前は武運長久を祈り、釜の蓋や鍋を持ったり被ったりして神社に祈願すると、敵の鉄砲の弾が当たらず無事に帰還できるという言い伝えがあったとか。これにより、当時は出兵者やその家族が多く参拝に訪れたそうです。
釜の蓋を頭に載せて祈願するユニークな「釜蓋願掛け」や、素焼きの釜蓋を投げる「釜蓋投げ」は、勝負事や開運・開拓・厄除け・武運長久にご利益があると言われています。現在ではスポーツ選手・芸能人をはじめ、全国から多くの参拝客が足を運んでいます。
鹿児島県南九州市頴娃町別府6827
8時~18時
なし
【電車】JR頴娃大川駅より徒歩15分【車】指宿スカイライン頴娃ICより20分
あり(無料)
「釜蓋神社(射楯兵主神社)」の詳細はこちら
「釜蓋神社(射楯兵主神社)」の口コミ・周辺情報はこちら
\こちらの記事もチェック/
\宿・ホテル検索はこちら/
※この記事は2024年11月20日時点での情報です。休業日や参拝時間など掲載情報は変更の可能性があります。
※掲載されている情報や写真については最新の情報とは限りません。必ずご自身で事前にご確認の上、ご利用ください。
※掲載の価格は全て税込価格です。
じゃらん編集部
こんにちは、じゃらん編集部です。 旅のプロである私たちが「ど~しても教えたい旅行ネタ」を みなさんにお届けします。「あっ!」と驚く地元ネタから、 現地で動けるお役立ちネタまで、幅広く紹介しますよ。