第六章<ときは、今> 京都【京都府京都市】
謎多き本能寺の変。現地を訪ねて人生を思う。
いよいよ舞台は最終章・京都へ。天正十(1582)年6月2日、明智軍は亀山城から老ノ坂を越えて京の本能寺へ向かう。直前の5月末には愛宕神社で連歌会を催し「時は今 あめが下しる(なる) 五月哉」のあの句を詠んだ。
現在でも謎に包まれた本能寺の変。パワハラ説、黒幕説、四国問題説など新説は後をたたないが、旅を通してひとりの戦国武将が何かの思いをもって京へ向かったのは確かだと思えた。これにて明智光秀の人生を辿る旅の幕を閉じよう。
<本能寺へ>
[アクセス]【電車】京都市営地下鉄市役所前駅より徒歩2分【車】名神高速京都南ICより20分
\ゆかりの地/法華宗大本山本能寺【京都府京都市】





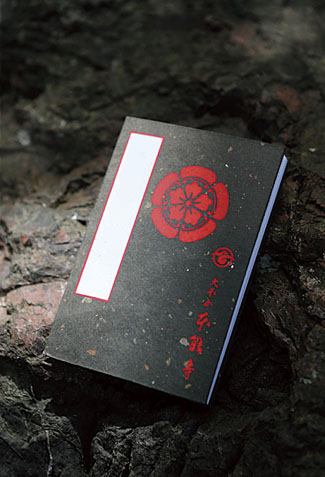
いざ、本能寺へ様々な思いが駆け抜ける。
本能寺の変後、豊臣秀吉の命により現在の場所に移転。信長の三男信孝により建てられた信長公廟が残る。宝物館では信長所有の天目茶碗や唐銅香炉「三足の蛙」などの名品を展示。
[TEL]075-231-5335
[住所]京都府京都市中京区寺町通御池下ル下本能寺前町522
[営業時間]6時~17時、大寶殿宝物館9時~17時(最終入館16時30分)
[定休日]なし、宝物館は年末年始・展示替え日
[料金]参拝無料、宝物館500円
[駐車場]20台(30分200円)
「法華宗大本山本能寺」の詳細はこちら
\ゆかりの地/大本山妙心寺【京都府京都市】



1337年創建の臨済宗妙心寺派の大本山で京都最大の禅宗寺院。特別公開で拝観できる浴室は「明智風呂」とも呼ばれ、光秀の叔父・密宗和尚が光秀の菩提を弔うために創建されたといわれる。
<非公開文化財特別公開>
2020年1月10日~3月18日の期間、「京の冬の旅」キャンペーンでは「明智光秀と戦国の英傑たち」と称して特別公開を実施。妙心寺(明智光秀)、大徳寺総見院(織田信長)、高台寺(豊臣秀吉)、知恩院(徳川家康)などで通常非公開の文化財を見学できる(1カ所600円 一部期間・料金異なる)。定期観光バスも運行予定。問い合わせ:京都市観光協会[TEL]075-213-1717
[TEL]075-466-5381
[住所]京都府京都市右京区花園妙心寺町1
[営業時間]法堂・大庫裏9時10分~11時50分、12時30分、13時~16時40分の20分毎(11月~2月は15時40分迄)
[定休日]なし
[料金]拝観料大人700円
[駐車場]80台
「大本山妙心寺」の詳細はこちら
\ゆかりの地/餅寅【京都府京都市】




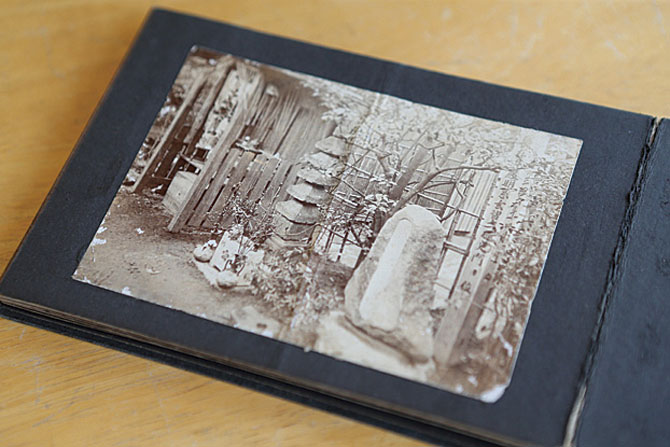

250年間光秀の首塚を守り続ける和菓子店。
天保年間より続く餅寅では、江戸中期から現在に至るまで代々光秀の首塚といわれる梅宮社を守り続けている。明智塚にお参りしたら、餡たっぷりの光秀饅頭を。
[TEL]075-561-2806
[住所]京都府京都市東山区白川筋三条下る梅宮町475
[営業時間]9時~17時
[定休日]不定※電話確認がベター
[駐車場]周辺有料駐車場利用
「餅寅」の詳細はこちら
\グルメ/本家尾張屋【京都府京都市】




宝を集める縁起の良い名物「宝来そば」を味わう。
1465年に尾張から京へ来て550年余り。京都の良質な地下水と音威子府(おといねっぷ)のそば粉で打つ二八そばが5段の漆器に盛られ、一椀ごとに違う薬味で楽しめる。
[TEL]075-231-3446
[住所]京都府京都市中京区車屋町通二条下る
[営業時間]11時~19時( LO18時)※お菓子販売は9時~
[定休日]1月1日、2日
[駐車場]周辺有料駐車場利用
「本家尾張屋」の詳細はこちら
\ゆかりの地/亀屋陸奥【京都府京都市】


合戦の兵糧代わりだった?京都銘菓「松風」。
1421年創業。本願寺の御供物司として代々菓子を納める。1570年の石山本願寺と信長の合戦の際、僧たちの兵糧代わりとなったのがはじまりとも。
[TEL]075-371-1447
[住所]京都府京都市下京区西中筋通七条上る菱屋町153
[営業時間]8時30分~17時
[定休日]水、ほか臨時休業日あり、1月1日~3日
[駐車場]周辺有料駐車場利用
「亀屋陸奥」の詳細はこちら
※この記事は2019年10月時点での情報です
■消費税の税率変更に伴うお知らせ
※2019年10月11日時点の10%消費税込金額で記載しております。
消費税率10%への引き上げに伴い、施設利用時に現地にて価格変更が発生する場合がございます。
実際のお支払い金額に関しましては、ご利用いただく施設までお問い合わせください。
じゃらん編集部
こんにちは、じゃらん編集部です。 旅のプロである私たちが「ど~しても教えたい旅行ネタ」を みなさんにお届けします。「あっ!」と驚く地元ネタから、 現地で動けるお役立ちネタまで、幅広く紹介しますよ。























