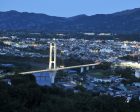大阪のパワースポットをご紹介!定番から穴場まで。レンタカーでドライブしながらパワースポット巡りをしてみては?観光にもおすすめ!
街中にありながら、厳かな雰囲気でたたずむ歴史ある神社や、静寂で凛とした空気を感じられるような神社も!パワースポットが盛りだくさん!
記事配信:じゃらんレンタカー
※紹介施設はじゃらんnet観光ガイドから抜粋しました
※掲載されている情報や写真については最新の情報とは限りません。必ずご自身で事前にご確認の上、ご利用ください
四天王寺

出典:じゃらん 観光ガイド 四天王寺
1400年前の推古天皇元年(593)、物部守屋と蘇我馬子の合戦に勝利したことを受けて、聖徳太子が四天王を安置するために建立したと伝えられる、日本初の本格的な仏教寺院。その伽藍配置は大陸の影響を色濃く受けた「四天王寺式伽藍配置」といわれるもので、南から北へ向かって中門、五重塔、金堂、講堂を一直線に並べ、それを回廊が囲む形式。日本では最も古い建築様式のひとつだそうだ。仏教の根本精神の実践の場として、中心伽藍の北には、仏法修行の道場である「敬田院」、病者に薬を施す「施薬院」、病気の者を収容し病気を癒す「療病院」、身寄りのない者や年老いた者を収容する「悲田院」の四箇院が設けられている。その後、幾度の戦禍と災難によって伽藍は焼失へ。現在の伽藍は昭和38年(1963)、当初のものを厳密に再興したものだそうだ。全敷地面積33,000坪、甲子園球場の3倍の広さをもつ四天王寺の境内には、聖徳太子を祀っている「太子殿」や、近畿三十六不動尊第一番の霊場の「亀井不動堂」、日本庭園の「極楽浄土の庭」など、たくさんの見どころが。また毎年4月22日、聖徳太子を偲んで行われる「聖霊会舞楽大法要」では、「天王寺舞楽」が舞われている(国の重要無形民俗文化財)。
\口コミ ピックアップ/
鳥居をくぐって入った先には、お寺。五重の塔。不思議な空間でしたが、パワーを感じました。歴史的な意味もあり、素晴らしい。一度は訪れたいパワースポットです。
(行った時期:2018年2月)
敷地は割と広く、五重塔や金堂、庭園などがあります。近くの通りは街中とは思えない懐かしい雰囲気があります。大阪七福神の札所である布袋堂があり、乳のおんばさんのお堂と呼ばれ、「子どもが健康に育つように」「お乳がよく出ますように」と願いを書いた絵馬が多く吊り下げられています。
(行った時期:2017年1月8日)
所在地 〒543-0051 大阪府大阪市天王寺区四天王寺1-11-18
交通アクセス (1)地下鉄谷町線「四天王寺前夕陽ヶ丘駅」から徒歩で5分
営業期間 営業:4~9月 8:30~16:30 *毎月21・22日 ~17:00 10~3月 8:30~16:00 *毎月21・22日 ~16:30 六時堂 8:30~18:00 *毎月21・22日 8:00~ 本坊庭園 9:00~16:00
定休日:年中無休(庭園の臨時休園日あり)
料金 備考:中心伽藍:大人300円、高大生200円 宝物館:大人500円、高大生300円 本坊庭園:大人300円、高大生200円
その他 駐車場(50台(バス可)有り 普通車:1時間500円、以降30分毎250円)
「四天王寺」の詳細はこちら
厳島神社(枚方)

出典:じゃらん 観光ガイド 厳島神社(枚方)
本殿右側には、厳島神社末社春日神社本殿があり、これは幕末の頃奈良の春日大社旧殿を厳島神社本殿として譲り受けた際に、元の厳島神社本殿を移築したものです。造築年代は不明ですが、建築様式から室町中期~後期と推定されています。造りは一間社流造りで桧皮葺きの屋根、など、京都府に近いこともあり、大阪府南部とは少し異なった地域的特色が出ています。また厳島神社末社春日神社本殿は、1978年(昭和53年)に国の重要文化財に指定されました。
\口コミ ピックアップ/
神社の真っ赤な鳥居がとっても印象的でした。
厳かな雰囲気が境内から漂っていました。
参拝していても、とっても癒されました。
(行った時期:2018年5月)
歴史ある厳島神社。とても神聖な場所でなんだか不思議な気持ちになりました。子どもにもとても勉強になる所です。
(行った時期:2016年7月)
所在地 〒573-0112 大阪府枚方市尊延寺5-9-11
交通アクセス (1)JR学研都市線「津田駅」下車
営業期間 休業:無休
「厳島神社(枚方)」の詳細はこちら
磐船神社(交野市)

出典:じゃらん 観光ガイド 磐船神社(交野市)
大阪府の東北部、交野市を南北に流れる天の川の上流にあり、高さ12m、幅12mの船形の巨岩「天磐船(あめのいわふね)」をご神体とする神社。言い伝えによると、物部氏の祖神とも言われる饒速日命が高天原からこの地に降臨した時、用いていた舟が石となり、神格化したという。大阪城築城の際、加藤清正がこの巨岩を運び出そうとしたが叶わず、岩の上に「加藤肥後守清正」と刻み、断念したとも。御神体のそばにある巨岩には、天の川に面して大日如来、観音菩薩、地蔵菩薩、勢至菩薩の4体の仏像が彫られている。古来より神道家や修験道の行場として知られる同社では、巨岩の下に広がる岩窟内に入る「岩窟めぐり」も行なわれていて、一般の参拝者も体験することができる。
\口コミ ピックアップ/
ご神体である巨岩に圧倒されます。近年パワースポットとして有名になったのでちょっと雰囲気が損なわれた気がします。静かな聖地です。
(行った時期:2016年9月)
巨大な石が有名な神社でパワースポットとして最近賑わっています。ちょっと元気が足りないなと思った時に来ると良いと思います。
(行った時期:2016年9月)
所在地 〒576-0033 大阪府交野市私市9丁目19ー1
交通アクセス (1)京阪交野線「私市駅」下車 京阪バスまたは奈良交通バスに乗換「磐船神社前」バス停下車、近鉄「生駒駅」下車 奈良交通バス 北田原方面行きに乗換 終点「北田原」バス停徒歩10分
営業期間 営業:岩窟拝観は要問合せ
料金 備考:岩窟拝観は要問合せ
「磐船神社(交野市)」の詳細はこちら
犬鳴山

出典:じゃらん 観光ガイド 犬鳴山
泉佐野市に位置する犬鳴山には、約1300年前に役行者によって開祖された日本最古の修験根本道場・犬鳴山七宝滝寺のほか、温泉街などがあることで知られる。山内では「山内二十八宿」として、主要な行場、滝、岩、堂、祠などを巡行できるように整備されており、多くの人が修行に触れられるようになっている。犬鳴山は「女人大峯」とも呼ばれ、女性も修行できる行場として有名だ。犬鳴山の名は、宇多天皇の時代(887-897)、山中で大蛇に狙われた猟師を、その愛犬がけたたましく吠え、身を挺して主人を守ったことから名付けられたという。犬鳴山七宝滝寺へ向かう道筋に、名犬・義犬の墓が建てられている。また、犬鳴山の麓の渓流沿いにある温泉街では、春は山桜、夏はホタルに河鹿(カジカガエル:鳴き声が雄鹿に似ていることから)、秋は紅葉、冬はちらつく雪と四季それぞれの趣があり、静かな山里情緒にあふれている。
\口コミ ピックアップ/
自然豊かな場所にあり、たくさんパワーをもらえます。
夏に行きましたが涼しく過ごしやすい感じでした。
(行った時期:2014年8月)
所在地 〒598-0023 大阪府泉佐野市大木
交通アクセス (1)南海本線「泉佐野駅」から
(2)JR阪和線「日根野駅」からバスで(南海バスで「犬鳴山」下車)
「犬鳴山」の詳細はこちら
露天神社(お初天神)

出典:じゃらん 観光ガイド 露天神社(お初天神)
梅田の「お初天神通り商店街」を南へ行き当たると、ビルの谷間に露天神社(つゆてんじんじゃ)がある。創建は、1300年以上遡るといわれ、少彦名(すくなひこな)命と菅原道真を祭神とする、梅田・曽根崎(古くは曽根洲と呼ばれた)の総鎮守。昌泰4年(910)、菅原道真が太宰府へ左遷配流される途中、当社に立ち寄って「露と散る 涙に袖は 朽ちにけり 都のことを 思い出ずれば」という歌を詠んだことにちなんで、「露天神社」と称するようになったと伝えられている。一方、通称の「お初天神」は、近松門左衛門が、元禄16年(1703)4月7日に、当社「天神の森」で起こった、堂島新地天満屋の遊女「お初」と内本町平野屋の手代「徳兵衛」の情死事件を題材に、「曽根崎心中」を劇化して大評判になり、大勢の参拝者が訪ねたことに由来する。現在も、恋の成就を願う多くの人々が訪れている。毎月第1・第3金曜日には、「お初天神蚤の市」が開かれ、特色ある古物商約30店が軒を並べる。
\口コミ ピックアップ/
浄瑠璃や歌舞伎で有名な近松門左衛門作の曾根崎心中の事件現場だ。露天(つゆのてん)神社が正式の名前だが心中した遊女お初の名前で、お初天神と呼称されている。今ではパワースポットで縁結びのご利益が有り若い男女も多く訪れるようだ。
曽根崎お初天神通り商店街を進むと行き着きます。
(行った時期:2018年9月12日)
曽根崎心中で有名なお初天神。梅田からも近く、夜にいくと、なんとも言えない雰囲気が素敵です。縁結びのスポットでもあります。たくさん飲食店もあり観光にぴったりです。
(行った時期:2018年6月)
難波神社

出典:じゃらん 観光ガイド 難波神社
地下鉄御堂筋線「心斎橋駅」3番出口徒歩5分、反正天皇が仁徳天皇を偲んで建立したと伝えられる古社。もとは河内の地(現在の河内松原市)にあったが、秀吉が大阪城を築城した際に現在の地へ移転、その地名から「上難波神社」と称され、その後明治8年(1875)には現在の社名になっているという。江戸時代には、稲荷信仰の隆盛に伴い本社よりも境内の末社である稲荷神社、通称「博労町のおいなりさん」の方が有名だった。また、同じ境内でひときわ賑わっていたのが現在の人形浄瑠璃文楽座の名称の元となった稲荷社文楽座だ。植村文楽軒が始めた文楽座は江戸時代の文化8年(1811)から断続的に続き、明治4年(1871)に西区松島に移るまでこの地にあったという。その後、反文楽軒派の「いなり彦六座」がこの境内に移って、一時期は松島の文楽座をしのぐほどの勢いだったとか。毎年7月20・21日に行われる夏祭りは「氷室祭」といい、参拝者にはカチワリ氷が配られる。
\口コミ ピックアップ/
商売繁盛や家内安全などに効く神社だそうです。
なかなか素敵なパワースポットだと思いました。
鳥居の雰囲気が素敵でした。
(行った時期:2018年6月)
商売繁盛のご利益があると聞いて、近くに遊びに行った際に寄ってみました。思っていたより大きな神社で、雰囲気が清々しく都会の中にあるので癒しになります。
(行った時期:2018年7月)
所在地 〒541-0059 大阪府大阪市中央区博労町4-1-3
交通アクセス (1)地下鉄御堂筋線「心斎橋駅」3号出口から徒歩で5分
(2)地下鉄「本町駅」13号出口から徒歩で5分
営業期間 営業:7:00~18:00
定休日:なし
料金 備考:無料
その他 駐車場(10台スペース有)
「難波神社」の詳細はこちら
垂水神社

出典:じゃらん 観光ガイド 垂水神社
「石ばしる垂水の上の早蕨の萌え出ずる春になりにけるかも」志貴皇子が詠まれた垂水の滝があります。
650年ごろの干ばつの時に難波長柄豊碕宮に垂水の水を高桶で送ったと伝えられています。
吹田三名水のひとつです。
\口コミ ピックアップ/
垂水神社にはパワースポットとして、たくさんの人々がいらっしゃっていました。かなり賑わっていましたよ。
(行った時期:2018年10月)
垂水神社の鳥居をくぐり抜けて入り、のぞくと落葉樹の新緑がそこそこありました。よいパワースポットだと思いました。
(行った時期:2017年4月)
所在地 〒564-0062 大阪府吹田市垂水町1丁目24-6
交通アクセス (1)阪急千里線「豊津駅」より徒歩10分、地下鉄御堂筋線「江坂駅」より徒歩15分
「垂水神社」の詳細はこちら
野里住吉神社

出典:じゃらん 観光ガイド 野里住吉神社
JR塚本駅から南西へ500m。永徳2年(1382)、足利義満(あしかがよしみつ)の創建と伝えられる神社。野里という町は、明治末期の新淀川開削で、旧中津川の右岸(現西淀川)に沿って開かれた昔からある村落。同社には、「一夜官女」(いちやかんにょ)という珍しい神事がある(府の無形文化財)ことで知られる。野里の村は、昔から風水害や疫病に相次いで見舞われていたことから、村人は毎年旧暦1月20日に、娘を神に捧げる神事を行うようになった。それから7年目、村を通りかかった武士が退治に名乗り出て、娘の身代わりに生け贄のふりをすることに。翌朝、武士の姿はなかったが、血の跡をたどっていくとそこには大きな狒狒(ひひ)が死んでいた、という講談でよく語り継がれている「岩見重太郎の狒狒退治」が伝わる。現在の祭りが行われる2月20日には、氏子より選ばれた7人の少女が、美しく飾られた御供物の桶7台とともに神前に進み献じる。使用の道具には元禄15年(1702)の墨書のものがあり、古い神事であることが確認できる。また、境内の東側には、明治末期の堤防の遺溝がある。
\口コミ ピックアップ/
木々がどこまでも続いていて、神聖な雰囲気がする神社でした。
参拝をしている間も、心が研ぎ澄まされる心地がいたしました。
(行った時期:2018年6月)
所在地 〒555-0024 大阪府大阪市西淀川区野里1-15-12
交通アクセス (1)JR「塚本駅」から(南西へ500m)
「野里住吉神社」の詳細はこちら
枚岡神社

出典:じゃらん 観光ガイド 枚岡神社
大阪平野の東端、生駒山の西麓にある枚岡神社へは、近鉄奈良線枚岡駅から東へ歩いてすぐ。延喜式の神名帳にもその名がある河内国一ノ宮の古社で、創祀は神武天皇即位前3年と伝えられる。後に奈良の春日大社に枚岡神社の二分霊を祀ったことから「元春日」とも呼ばれている。本殿は豊臣秀頼が片桐且元に造営させたと伝えられるが、現在の本殿は1826年に再建されたもの。府下随一と言われる秋祭りは、ふとん太鼓の宮入や地車の曳行などが行なわれ、勇壮かつ華やか。毎年年末の12月23日に、新しいしめ縄を掛け替えて大勢で笑う「注連縄掛神事」(しめかけしんじ)通称「お笑い神事」が行われます。年初には、その年の稲の実りを、小豆粥を使って占う「粥占神事」が行なわれる。境内は楠、杉などの古木が多く、環境省の「かおり風景100選」に指定を受けた。毎春、境内南側の枚岡神社梅林では約500本の梅が咲き競う。
\口コミ ピックアップ/
大阪府東大阪市にある神社です。
毎年、年末に行われる「お笑い神事」が有名です。
近年パワースポットとしても有名です。
(行った時期:2015年12月25日)
暗峠を歩く際に立ち寄りました。パワースポットとしても有名な神社ですが、非常に立派な神社で、歴史を感じさせるたたずまいでした。
(行った時期:2014年9月)
所在地 〒579-8033 大阪府東大阪市出雲井町7-16
交通アクセス (1)近鉄奈良線「枚岡駅」から
料金 備考:拝観無料
その他 駐車場(40台 9:00~16:00)
「枚岡神社」の詳細はこちら
堀越神社

出典:じゃらん 観光ガイド 堀越神社
第33代・推古天皇の時代、四天王寺建立と同時期に、聖徳太子が叔父の第32代・崇峻(すしゅん)天皇を偲んで茶臼山に建立したと伝えられ、四天王寺七宮のひとつに数えられる神社。古くから明治中期まで境内の南沿いに美しい堀があり、この堀を越えて参詣したので、「堀越」という名がつけられたという。境内には、かつて八軒家の渡辺の津にあった熊野第一王子の窪津王子が祀られている。交通量の多い谷町筋に面しているが、樹齢数百年におよぶ樹木などによって、境内は閑静な雰囲気を保持している。大阪では、「堀越さんは一生に一度の願いを聞いてくださる神さん」との言い伝えがあり、古くから親しまれている。
\口コミ ピックアップ/
一生に一度だけ願いを聞いてくれる神様だと聞き、お願いごとをしに行ってみました。緑に囲まれていて、本殿はおごそかな雰囲気がしました。
(行った時期:2018年7月)
聖徳太子が崇峻天皇を偲んで、風光明媚な茶臼山の地に四天王寺建立と同時に創建建立。明治の中期まで境内南沿いに美しい堀があり、この堀を越えて参拝したとの事、「一生に一度の願いを聞いてくれる」と言い伝えがあるそうです。本当のお願い事はとっておこうかなと思いました。
(行った時期:2016年10月15日)
所在地 〒543-0063 大阪府大阪市天王寺区茶臼山町1-8
交通アクセス (1)地下鉄御堂筋線・谷町線・JR「天王寺駅」から徒歩で15分(約10~15分)
(2)近鉄「あべの橋駅」から徒歩で15分(約10~15分)
営業期間 営業:6:00~17:00
その他 駐車場(3台 無料)
「堀越神社」の詳細はこちら
※この記事は2018年11月時点での情報です
※掲載している情報が実際と異なる場合があります。実際の交通規制標識・表示等に従ってください

日本を楽しもう!
47都道府県の話題スポットや楽しいイベント、美味しいグルメなど、おでかけに関する様々な情報をご紹介します♪